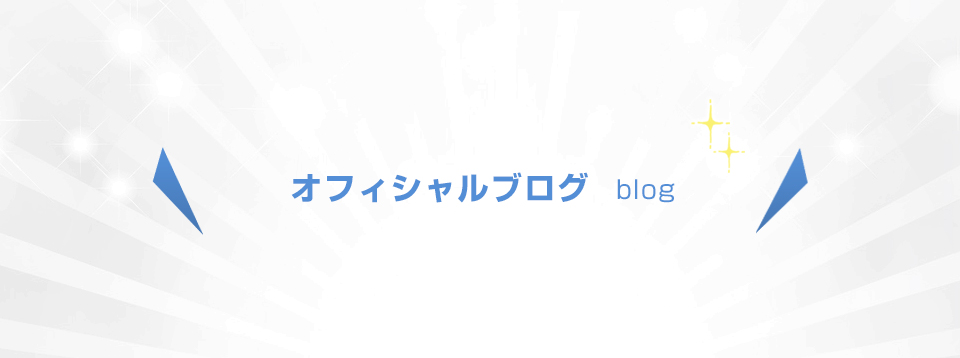皆さんこんにちは!
リサイクルショップ かたづけ屋の更新担当中西です♪
~現場から見るリサイクルの実態~
リサイクルの現場は、一般の人が想像するよりもはるかに複雑で、緻密な作業の積み重ねで成り立っている。
ここでは、リサイクル業がどのように資源を再生させているのか、現場の視点から解説する。
回収の段階
最初の工程は「回収」。
ここで重要なのは、品質を保ったまま資源を集めることである。
分別が不十分なまま混在してしまうと、再資源化のコストが跳ね上がり、品質も落ちてしまう。
リサイクル率を上げるには、家庭や事業所での“適正分別”が欠かせない。
選別と破砕
集められた廃棄物は、リサイクルセンターで種類ごとに分けられる。
鉄・アルミ・銅・プラスチック・紙・ガラスなど、素材に応じて専用の機械やラインが設置されている。
磁力選別機、風力分別機、光学センサーなどを使い、ミリ単位で仕分けを行う。
破砕後の素材は、再利用のために均質化され、次の工程へと進む。
この過程での“微細な異物除去”が、製品の品質を左右する。
再資源化の工程
破砕・選別された素材は、再び溶かされたり圧縮されたりして、新しい製品の原料となる。
金属なら再溶融、プラスチックならペレット化、紙ならパルプ化。
この工程を経て、再び社会に戻っていく。
再生素材は、自動車部品・建材・衣類・文房具など、身近な製品に姿を変える。
消費者が気づかぬうちに、再生資源が生活のあらゆる場面で活躍しているのである。
現場の課題
現場の最大の課題は、“混合・異物”である。
家庭ゴミの中に電池やガラス片が混入していると、機械破損や火災の危険がある。
また、リチウム電池による火災事故は全国で増加傾向にあり、正しい排出方法の周知が急務となっている。
このような現実を踏まえ、リサイクル業は「安全教育」「地域啓発活動」にも力を入れている。
現場を支える人々
リサイクル業の現場では、機械では代替できない“人の目”が最後の品質管理を担う。
小さな異物や素材の混在を見抜く目、手の感覚で分かる重さの違い、
それらを活かして高品質な再資源化を実現している。
「見えないところで社会を支える職人」としての誇りが、日々の作業に宿っている。